気づかないうちに「無力感の犬」になってませんか? その理由と乗り越える方法

気づかないうちに「無力感の犬」になってませんか? その理由と乗り越える方法
こんにちは!関達也です。
挑戦しようと思ったのに、どうしても一歩を踏み出せない経験はありませんか?
たとえば、資格試験に何度も失敗して挑戦を諦めた、転職を考えながらも行動に移せない…。こうした状況、実は「自分に行動する力がない」と思い込んでしまっている可能性があります。
実は、心理学者マーティン・セリグマンが提唱した「学習性無力感」という理論が、こうした心理状態の背景にあるかもしれません。
この記事では、セリグマンの理論をもとに、行動を止める無力感をどう克服できるのかを考えます。
「学習性無力感」とは何か?
1960年代、心理学者マーティン・セリグマンはある実験を行いました。この実験では、犬を2つのグループに分け、それぞれに異なる条件で電気ショックを与えたのです。
1つ目のグループは、スイッチを押すことで電気ショックを止められる仕組みでした。一方で、2つ目のグループは、どんな行動をしても電気ショックを止めることができず、ただ受け続けるしかありませんでした。
その後、両方のグループを「簡単に逃げられる状況」に置きましたが、最初に無力感を学習してしまった犬たちは、逃れる行動を全く取らなくなりました。
この実験から、「どんなに状況が改善されても、過去の失敗体験が行動を抑制してしまう」という現象が明らかになりました。
これが「学習性無力感」です。この理論はその後、人間の心理研究に応用され、特にうつ病やストレス対策の研究に役立てられています。
自分も「無力感の犬」になっていないか?

セリグマンの犬の話を聞いて、「自分には関係ない」と思ったかもしれません。
でも、日常の中で知らず知らずのうちに「学習性無力感」に囚われてしまうことは多いのです。
たとえば、
- 仕事での挑戦:提案が却下され続けて、「どうせまた失敗する」と思い込む。
- 健康管理:ダイエットや運動に何度も失敗し、「私は無理だ」と諦めてしまう。
- 地域格差:地方でチャンスが少ないと感じ、何も始めない。
僕自身も、地方で起業した当初は「地方では成功が難しい」という思い込みがありました。でも実際には、一歩を踏み出すことで状況は変えられるんですよね。
どうすれば行動に移せるのか?
学習性無力感を克服するにはどうすればいいのか?ここで重要なのは、小さな成功体験を積み重ねることです。
- 達成可能な目標を設定する:いきなり大きな目標を掲げるのではなく、まずは小さな行動から始める。たとえば、運動なら1日3分から。
- 環境を変える:新しい場所や人と関わることで、自分の可能性を再発見する。
- ポジティブ心理学を活用する:セリグマンは「感謝」「楽観」「目標志向」を強調しました。これを日常に取り入れるだけでも、自己効力感が高まります。
僕の場合も、まずは簡単なタスクをこなすことで「やればできる」という感覚を取り戻しました。そして、それを繰り返すことで少しずつ行動の幅が広がっていきました。
自分を取り戻すヒント

「他の人に比べて自分は…」と感じることも無力感を強めます。しかし、比較を正しい視点で行えば、自分を前向きに捉え直すことができます。
たとえば、海外の起業家は失敗を繰り返しながら成功を掴むことが当たり前とされています。一方、日本では失敗がネガティブに捉えられがちです。でも、視点を変えれば、失敗そのものが成長の過程なのです。
地方と都市の違いも同様です。地方は都市に比べてチャンスが少ないと感じることがありますが、その分競争も少なく、自分の工夫次第で大きな成果を上げることが可能です。
行動のすすめ
「無力感」は過去の思い込みにすぎないとしたら、あなたはどう行動しますか?
僕自身、何度も挑戦と失敗を繰り返してきましたが、行動を止めないことで新しいチャンスを掴んできました。そして、もう一度やり直してみたんです。
やらずに悩むより、一歩を踏み出すほうが状況は早く変わります。
たとえば、明日はちょっと早起きしてみるとか、そんな一歩でもいいんです。何かひとつ挑戦してみませんか?
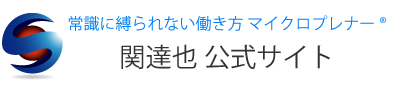

コメント