なぜ日本人は真似るだけで終わらないのか?応用力の秘密に迫る

なぜ日本人は真似るだけで終わらないのか?応用力の秘密に迫る
こんにちは!関達也です。
先日、迎賓館赤坂離宮の映像がテレビで流れてました。そのネオ・バロック様式を基調とした建物の壮麗さに圧倒されながらも、ふと疑問が浮かびました。
「なぜ日本人は他文化を単に真似るだけでなく、それを独自のものに昇華させることが得意なのだろう?」
歴史を振り返っても、日本人って他の文化をただ真似るだけじゃなくて、それを改良して独自のものにしちゃうのが得意ですよね。
漢字や仏教、そして黒船来航後の近代化なんかがその代表例です。そこでこの記事では、その秘密を掘り下げてみたいと思います。
日本人の応用力を示す具体例

日本人が他文化を取り入れて独自のものに進化させてきた事例をいくつか見ていきましょう。それぞれの例に、日本特有の工夫や適応力が垣間見えます。
漢字の導入と和製漢字
漢字って中国から伝わったんですが、日本人はそれをそのまま使うだけじゃ満足しなかったんですよね。訓読みや送り仮名を加えて、日本語にピッタリ合う形に進化させたんです。
それだけじゃなくて、「働」「峠」「畑」みたいな和製漢字まで作りました。これってすごくないですか?自分たちの文化や生活に合わせて新しい文字を作るなんて、普通思いつかないですよね。
仏教と神道の融合
仏教が伝わったのは6世紀頃ですけど、日本ではもともと神道があったんですよ。それで普通なら「どっちが正しいか」みたいに対立しそうなものなのに、日本では「両方取り入れちゃおう!」ってなったんです。
たとえば、神社の中に仏教的な装飾が施されていたり、「神仏習合」なんて形で神道と仏教が融合したり。
こういう調和の力って、日本人の特徴だと思いませんか?
黒船来航後の近代化
1853年に黒船が来たとき、日本人はとんでもなくびっくりしたはずです。でもその後がすごいですよね。西洋の技術や制度をガンガン取り入れて、あっという間に近代化を進めたんです。
明治維新以降は、鉄道や軍隊、教育制度なんかも取り入れつつ、日本独自のスタイルにアレンジ。これで「ただの真似」で終わらないのが日本人らしいですよね。
なぜ日本人は応用力があるのか?

こうやって見ていくと、日本人が持つ特有の力が見えてきます。どうしてこんなに応用力があるんでしょうか?
学びの姿勢
昔から「他国から学ぶ」姿勢が強かったんですよね。遣唐使とか留学生が中国に行って、たくさんのことを持ち帰ってきました。
この「学びたい!」という意識が他文化を吸収する原動力になっています。
改良志向
ただ真似するだけじゃなくて、「これ、もっと良くできるんじゃない?」って考えるんですよね。
トヨタ生産方式なんかもその一例で、フォード方式をベースにしながら、日本独自の改善を加えて世界トップレベルに仕上げました。
文化的適応力
異なる文化を調和させる力も、日本人ならではです。仏教と神道の融合や、迎賓館赤坂離宮みたいな建築も、この力の表れだと思います。
日本人の応用力は現代も活かせるはず!

こうやって振り返ると、日本人の応用力って「学び」「改良」「適応」がカギになってるのが分かります。
この応用力、今の時代にも活かせると思いませんか?
たとえばAIとかデジタルトランスフォーメーション(DX)は、日本が遅れ気味って言われてますけど、過去みたいに積極的に取り入れて進化させればチャンスはたくさんあると思うんです。
地方創生とか高齢化社会みたいな日本特有の課題をAIで解決する方法を考えれば、世界に先駆けたアイデアを生み出せるかもしれませんよね。
僕たちは今、AIのような新しい技術や文化にどう向き合い、何を学び、どう応用していけばいいんでしょうか?
僕はこれを考える中で、「とりあえず試してみる」ことがすごく大事だと思うんです。
迎賓館赤坂離宮や黒船来航から学んだ応用力を、僕ら自身の生活や仕事にどう活かせるか、あなたも考えてみませんか?
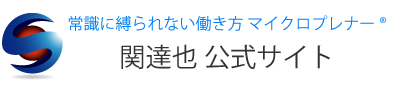
コメント