なぜ「ひとり親」の貧困率が高いのか?見えない壁とその理由

なぜ「ひとり親」の貧困率が高いのか?見えない壁とその理由
こんにちは!関達也です。
「ひとり親って大変そう」という言葉をよく耳にしますが、実際にひとり親になってみると、その大変さは想像以上です。
僕自身、2020年以降、ひとり親として生活しながら仕事と育児を両立する日々を送っていますが、常に時間との戦いであり、気が抜けない毎日です。
そこで今回は、ひとり親の生活がなぜこれほどまでに厳しいのかを、僕の経験を交えながら掘り下げてみたいと思います。
ひとり親家庭が直面する数字と現実

厚生労働省の調査によると、日本のひとり親家庭の貧困率は約48%と非常に高い水準です。これは先進国の中でも突出しており、特に母子家庭の平均年収は約243万円とされています。
僕自身もこの数字の重さを実感しています。ひとり親で仕事をフルタイムでこなしても、収入が十分とは言えないことが多いです。
この背景には、子育てと仕事を同時にこなさなければならない状況があります。保育園や学童保育の利用時間が限られているため、長時間労働ができず収入が伸びないという悪循環に陥りがちです。
僕も仕事と娘のサポートを両立する中で、この壁にぶつかっています。家での学習や日常生活のサポートに時間を割いており、習い事や学校行事にも関わることがあります。それに合わせた働き方を工夫する必要があり、結果として時間の使い方を常に見直し、柔軟な働き方を模索する日々です。
社会の仕組みに問題があるのでは?
ここで一つの仮説を立てます。
ひとり親がこれほど大変な理由の一つは、「社会の仕組み自体がひとり親向けに設計されていない」という点です。
しかし、ここで疑問が生じます。なぜ社会の仕組みはこれほど長い間、変わらないままなのでしょうか?
多くの企業が「残業できる人」「土日も働ける人」を評価する文化を持つ中、育児を一手に引き受けるひとり親は不利な立場に置かれています。この背景には、伝統的な価値観や固定観念が根強く残っていることが考えられます。
制度を変えるには、まずこの根本的な部分にアプローチする必要があるのかもしれません。
さらに、地方と都市部の違いも見逃せません。
都市部では保育園の数が多く、待機児童問題はあれど選択肢は広がります。一方で、地方ではそもそも保育園の数が限られており、通園時間が長くなるケースも珍しくありません。結果として、仕事と家庭のバランスがさらに難しくなります。
地方と都市、そして国際的な違い
僕が宮崎で生活しながら東京とも関わる中で気づいたのは、都市部の利便性と地方の不便さのギャップです。
東京では24時間営業の保育施設が増えてきていますが、地方では夜7時には閉まる保育園がほとんど。ひとり親が夜間や休日に働きたくても、その選択肢が極端に少ないのが現状です。
さらに、国際的に見るとスウェーデンなどの北欧諸国では、ひとり親への支援が手厚く、育児休暇や保育制度が充実しています。日本も見習うべき点は多いと感じます。
ひとり起業の可能性とオンラインでの仕事

ひとり親として生活する中で、僕が特に感じるのは「時間の自由」がどれだけ重要かということです。
そこでおすすめしたいのが、オンラインでできる仕事やひとり起業の道です。インターネットを活用することで時間や場所に縛られない働き方が可能になります。自宅でできる仕事が増え、通勤の負担がなくなるだけでなく、自分のスキルを世界に向けて発信できるチャンスも広がります。
例えば、ライティング、動画編集、オンライン講師、Webデザインなどは比較的少ない資本で始められます。僕自身もオンラインでの仕事を増やし、少しずつ単価を上げていくことで収入増を図っています。クラウドソーシングサイトを活用すれば、仕事を見つけるハードルも下がります。
ひとり親にとって、収入を増やすための工夫が不可欠です。オンラインでの仕事はその手段の一つとして、非常に有効だと感じています。
ひとり親が未来を切り拓くためにできること
ひとり親の生活が大変なのは、本人の努力不足ではなく、社会の構造的な問題が大きく関わっています。だからこそ、僕らができることは「仕組みを変えるための声を上げること」と「地域コミュニティでの助け合い」です。
また、自分自身でできることとして、オンラインでの仕事やひとり起業を検討してみるのも一つの選択肢です。僕が提唱する『ひとり起業家』の考え方は、ひとり親でも自由なライフスタイルを実現する可能性を秘めています。
僕自身、ひとり親としてこれからも自分の生活をより良くするために行動し続けます。起業することで、自分の時間をより自由に使え、育児と仕事のバランスを取る選択肢が広がるのです。
あなたの身近にもひとり親の友人や同僚がいるかもしれません。彼らが直面している課題を知り、何か手を差し伸べるきっかけになれば幸いです。
あなたはどう思いますか?
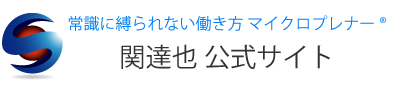
コメント