テレビの偏向報道とSNSの光と影!情報を見極める3つの視点

テレビの偏向報道とSNSの光と影!情報を見極める3つの視点
こんにちは!関達也です。
最近、テレビ報道が「偏向」とか「情報操作」って批判されること、増えてますよね。
たとえば、石丸伸二氏や斎藤兵庫県知事に関する報道の仕方に疑問を感じる声もあります。
その背景には、スポンサーや芸能事務所など特定の利害関係者の影響が指摘されています。また、SNSやYouTubeの台頭により、テレビの報道姿勢が暴露され、視聴者の疑念が増しています。
こうした現象は情報社会の光と影を浮き彫りにしています。
テレビ報道の問題とSNSの時代にどう向き合えばいいのか、一緒に考えてみましょう!
なぜテレビ報道の「偏向」が問題視されるのか?
テレビ報道に対する批判が増えている背景には、視聴者が抱く疑問や不安があると思います。
「なぜ一部の問題が取り上げられ、一部が取り上げられないのか?」「誰がその基準を決めているのか?」こうした疑問を掘り下げることで、報道の偏向をめぐる本質的な課題が見えてきます。
1. スポンサーと視聴率の影響
テレビ局って広告収入がメインだから、スポンサー企業にとって都合が悪い内容って、どうしても避けがちなんですよね。また、視聴率を重視するあまり、話題性の高いニュースやスキャンダルが優先され、長期的かつ深刻な社会問題が軽視されることもあります。
2. 芸能事務所との関係
芸能報道では、タレントを抱える事務所の意向が強く影響します。結果として、事務所にとって不利な情報が報じられない、あるいは操作された形で伝えられるケースもあります。
3. 視聴者の選択的摂取
さらに、視聴者自身にも「自分が信じたい情報だけを受け入れる」という選択的摂取の傾向があります。これにより、テレビの報道内容が「偏向している」と感じられる一因となります。
SNSやYouTubeの台頭がもたらす光と影

SNSやYouTubeが登場したことで、テレビ報道の限界を補う場面が増えましたよね。でも、同時にリスクも出てきていて、僕たちが新しいメディアをどう活用するかがカギになってきます。
僕自身、8年ほど前にSNSの危うさを感じて、オンラインサロンで正しい情報を見極める重要性を語ったことがありますが、今のほうがその影響力はさらに増していると感じます。
SNSの良い面
- 情報の多様性
個人が自由に情報を発信できるSNSやYouTubeでは、テレビが取り上げない視点や声が明らかになることがあります。たとえば、事件の被害者が直接SNSで証言を発信して、これまで知られてなかった事実が明らかになることもありますよね。 - リアルタイム性
災害や緊急事態において、SNSは迅速な情報伝達手段として重要な役割を果たします。テレビよりも早く現地の状況を知ることができるケースも少なくありません。
SNSの怖い面
- フェイクニュースの拡散
一方で、事実確認が不十分な情報や意図的に捏造された情報が流れるリスクがあります。こうした情報が拡散されると、誤解やパニックを引き起こす可能性があります。 - アルゴリズムの影響
SNSやYouTubeのアルゴリズムは、ユーザーが関心を持つ情報を優先的に表示します。その結果、自分と異なる視点に触れる機会が減り、ますます偏った視点を持つリスクがあります。
情報社会で生き抜くための3つの視点
テレビ報道の偏向やSNSのリスクを考えると、僕たちはどのように情報と向き合うべきでしょうか?
以下の3つの視点が重要です。
1. 多様な情報源を活用する
テレビだけでなく、新聞、SNS、YouTube、海外メディアなど、多様な情報源から情報を収集し、比較する習慣をつけることが大切です。一つのメディアに依存せず、異なる視点を取り入れることで偏りを防ぎます。
2. 批判的思考を持つ
どんな情報もそのまま信じるんじゃなくて、「これってなんで報じられたんだろう?」「裏にはどんな意図があるんだろう?」って考えるクセをつけたいですね。
たとえば、「この情報の出所は信頼できるか?」「他の情報源と矛盾していないか?」を確認することや、情報をファクトチェックするウェブサイトを活用するのも有効です。情報の背景を考えることで、より正確な判断ができます。
3. 自分も発信者になる
今って、僕たちは情報の受け手だけじゃなくて、発信者にもなれる時代に生きてるんですよね。ブログやSNSで自分が調べた事実や考えを発信することで、情報の一方通行を防ぎ、社会の情報循環に参加できます。
あなたはどう考える?

テレビ報道が偏向していると感じる背景には、スポンサーや視聴率、視聴者のバイアスといった多くの要因が絡み合っています。一方、SNSやYouTubeが情報の多様性を広げる一方で、フェイクニュースやアルゴリズムの影響といった新たな課題もあります。
結局、大事なのは、僕たちが「どの情報を信じるのか?」をちゃんと選んで、自分なりに行動することだと思うんです。情報社会の中で、何をどう受け取り、どう活用するかが問われています。
あなたはどう感じますか?この情報社会で、どんな行動を起こしますか?例えば、情報源の多様化を図ったり、SNSやYouTubeでの発信を試みたりするのも一つの方法です。まずは、日々のニュースに対して「なぜ?」と問いを立てることから始めてみませんか?
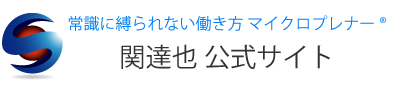
コメント