ひとり親の苦悩。アドラー心理学「課題の分離」で心を軽くしよう

ひとり親の苦悩。アドラー心理学「課題の分離」で心を軽くしよう
こんにちは!関達也です。
僕は娘を育てるひとり親、シングルファザーです。気づけばもう5年目。
仕事、家事、育児など全部ひとりでこなすのって、想像以上に大変ですよね。
「僕がしっかりしないと」「全部僕の責任」って思い込んで、自分のことよりも娘のことばかり考えてました。
娘の日々の健康はもちろん、僕の責任もあって引きこもりになった娘の今や将来についての不安が、いつも頭の中をぐるぐる回って、心が休まることがなかったんです。
娘が少しでも悩んだり困っていたりする様子を見れば、「僕がもっと助けなきゃ」って焦る。でも、どれだけ頑張っても、不安は消えません。
もしかしたら、この記事を読んでいるあなたも、同じような気持ちになっているかもしれません。「ひとりで何とかしないと」って気を張りすぎて、気づけば心も体もクタクタになっていませんか?
僕もそうでした。でも、あるときふと思ったんです。
「僕は娘の人生までコントロールしようとしているんじゃないか?」って。
この気づきが、僕の子育てを変えるきっかけになりました。
アドラー心理学の「課題の分離」とは?
ふと思い出したのがアドラー心理学の「課題の分離」という考え方でした。この考え方を知ったとき、「ああ、僕は自分の課題と娘の課題をゴチャ混ぜにしてたんだな」ってハッとしたんです。
アドラー心理学では、「これは誰の問題なのか?」を明確にするのが大事だと言われています。
例えば、
- 娘が勉強するかどうか → 娘の課題
- 娘が友達とうまくやれるか → 娘の課題
- 僕が娘のために環境を整える → 僕の課題
つまり、「親ができるのはサポートまで」で、「子どもが実際に行動するかどうかは、子どもの課題」ということなんです。
僕はこれまで、娘のことを思うあまり、「勉強しなさい」って言ったり、「将来困るよ」ってプレッシャーをかけたりしていました。でも、それって「娘の課題」に踏み込みすぎていたんですよね。
「課題の分離」をひとり親の視点でどう活かすか?
では、親はどこまで関わればいいのか? どうやって子どもと向き合えばいいのでしょう?
子どもの人生は子どものもの
親がいくら心配しても、最終的にどう生きるかは子どもの選択。
できるのは「サポート」までと考えて、過干渉はやめる。
「やるかやらないか」を子どもに委ねる
例えば、宿題をやるかどうかは子どもの課題。親ができるのは、「やりやすい環境を整える」「質問に答える」こと。
無理にやらせようとすると、親子関係がギスギスしてしまうこともありますよね。
自分の人生にも目を向ける
ひとり親って、「親である自分」にばかり意識がいきがちですよね。でも、自分の人生も大事なんです。
趣味を持ったり、リラックスする時間を作ったり、「自分の課題」にもしっかり目を向けることが大切なんです。
僕の実践例:課題の分離をどう乗り越えたか
「課題の分離」を意識することで気持ちは楽になっていきました。
例えば、僕と娘はキャンピングカーで1年以上生活していました。その後、娘は全く学校に行かず引きこもるようになりました。
しばらくずっと「このままでいいのか?」と悩みましたが、アドラーの考え方を思い出し、「学校に行くかどうかは娘の課題」と割り切ることにしたんです。
僕にできるのは、無理に行かせようとするのではなく、娘が安心して過ごせる環境を作ることでした。
具体的には、学校へ行かないことを否定せず、娘がやりたいことに耳を傾けるようにしました。
そして、娘が好きなことに没頭できる時間を確保したり、一緒に新しい体験をする機会を増やしたりしました。そう考えたら、肩の力が抜けました。
もともと父娘の仲は悪くなかったですが、娘のペースを尊重することで、お互いの状態は良くなっていったんです。
「課題の分離」をしても不安がぶり返すとき
「課題の分離」を理解して、気持ちが楽になったとしても、しばらくするとまた不安が襲ってくることがありますよね。
不安を完全になくすことはできませんが、その不安とうまく向き合う方法を知っていれば、振り回されにくくなります。
ここでは、不安を乗り越えるためのアドラーの考え方を紹介します。
不安は消すものではなく、向き合うもの
アドラー心理学では、不安に対して「目的論」という考え方を大事にしています。不安をなくそうとするのではなく、不安があってもどう行動するかを考えることが重要なんです。
例えば、「子どもが将来困らないか不安」と思ったとき、アドラーの考え方では 「じゃあ、今できることは何?」 って考えるんです。不安をなくそうとするんじゃなく、不安があっても自分ができることをやる。この思考法が大切なんですよね。
自己受容の大切さ
不安を抱くのは当たり前のこと。でも、「完璧な親でいなくてもいい」と受け入れることができれば、不安に振り回されにくくなるんです。
共同体感覚を持つ
さらに、アドラーが最終的に大切にしているのが「共同体感覚」です。これは、「自分は社会の一員であり、周りとつながっている」と感じることなんです。
ひとり親は、「全部自分でやらなきゃ」と思いがちですよね。でも、実際には僕たちはひとりじゃないんです。
例えば、
・同じひとり親の仲間とつながる
・友人や親戚に話を聞いてもらう
・「子どもは社会の中で育っていく」と考え、親がすべてをコントロールしようとしない
アドラーは、「自分ひとりで問題を抱え込まず、他者とのつながりの中で生きることが大切」だと考えています。
「自分はひとりじゃないし、子どもも社会の中で成長していく」と考えられたら、少しは気持ちが楽になるはずです。
ひとり親こそ「課題の分離」で心を軽く

もともと自分の人生楽しんでなんぼという信念で生きてきた僕でしたが、ひとり親になって4年以上、娘のことしか考えられませんでした。
でも、ひとり親って、全部を背負う必要はなかったんです。
「親の課題」と「子どもの課題」を分けることで、心がずっと楽になります。まだまだ完璧ではありませんが、僕自身、娘との関係を大切にしながら、ようやく自分の人生も楽しむことができるようになってきました。
今では、娘もどんどん自立してきて、自分で考えて行動することができるようになりました。課題の分離を意識することで、父娘関係もより良いものになったと実感しています。
あなたは、どの課題を手放せそうですか?
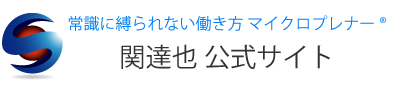

コメント