炎上した人はなぜ消えない?─テレビとネットの矛盾する倫理観

炎上した人はなぜ消えない?─テレビとネットの矛盾する倫理観
こんにちは!関達也です。
前回の記事では、「ニューメディアの中にも“フリーメディア”と“カオスメディア”がある」という話をしました。情報の自由さが魅力のニューメディアですが、その中でも発信の姿勢や情報の質は大きく異なるんです。
「フリーメディア」と「カオスメディア」についてはこちらの記事に書きました。
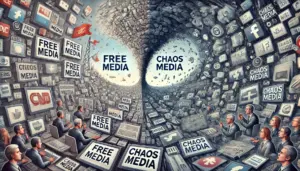
そして今回のテーマは、そのニューメディアの中で特に目立つ現象である「テレビで炎上・抹殺された人が、なぜかネットでは復活する」についてです。
たとえば、不祥事でテレビから姿を消したタレントが、YouTubeやNetflixで堂々と活動していたり、むしろ人気者になっていたりしますよね。
僕も最初は「え、なんでこの人まだ見かけるの?」って不思議だったんです。でも、これって今のメディアのあり方と、社会の倫理観の“ねじれ”が生んだ現象なんです。
今回は、その背景を「テレビとネットの倫理観の違い」から掘り下げていきます。
テレビの倫理観は「ホワイト社会」そのもの

テレビというメディアは、まさに“ホワイト社会”の代表です。
- スポンサーの意向が最優先(クリーンなイメージが命)
- 不祥事=即降板、CM契約解除、番組打ち切り
- 「一度の過ち」で社会的に抹殺される
たとえば芸能人が不倫したり、薬物に関わったりすると、番組は即降板。スポンサーが離れることを恐れて、番組側が先回りして自主的に処分する。まさに「正しくなければならない世界」ですよね。
この背景には、岡田斗司夫さんが言うように「ホワイト社会」の価値観が色濃くあるんです。
- 「間違いを犯した人は排除する」
- 「社会は清潔であるべき」
- 「子どもに見せても恥ずかしくない人間しか出してはいけない」
こうした価値観が、テレビの倫理を形作ってきたんです。
ホワイト社会についてはこちらの記事に書きました。

ネットの倫理観は「ストーリー社会」そのもの

一方、ネットは真逆なんです。どれだけ炎上しても「ストーリーがあれば生き残れる」社会です。
- 「謝罪動画」で視聴数が爆増
- 暴露話や裏話でチャンネル登録者数が急上昇
- 被害者ポジションに入ることで“同情”を獲得できる
不祥事を「物語化」することで、むしろ新しいファンを獲得する。まさに「ストーリー社会」の力なんですよ。
たとえば、テレビでは干されたタレントが、
- 「実はあのとき、こんな陰謀があった」と暴露
- 「自分はハメられた」「今だから真実を語る」と訴える
という展開で、視聴者の共感や支持を集めるんです。
「正しいこと」よりも「納得できるストーリー」があるかどうかが、ネットでは重要になる。だから炎上しても、そこから「再生の物語」を紡げる人は、ネットで生き残れるんですよね。
テレビとネット、倫理観のねじれが生むズレ

このテレビとネットの倫理観の違いが、「炎上=終わり」ではなく「炎上=始まり」になる構造を作っているんです。
テレビ:清潔さ・信頼性・スポンサー第一
- 失敗した人は「もう出すな」
- 信用を回復するには何年もかかる
ネット:話題性・共感・ストーリー第一
- 失敗した人こそ「語るべきネタを持っている」
- 「もう一度見てみたい」という声がファンを生む
この「ねじれ」のせいで、視聴者の中には混乱が起きていますよね。
「え? この人って干されたんじゃなかったの?」「テレビではダメだけど、ネットではOKなの?」って。
でもこの「ねじれ」が今のメディア社会の本質なんです。
炎上=終わり、ではなく「キャリアの転換点」

実際、炎上をバネにしてネットで再生した人って、かなり多いですよね。
例:宮迫博之さん
テレビでは謝罪会見後、表舞台から姿を消したけど、YouTubeではコラボやグルメ企画で大成功。
例:渡部建さん
地上波では姿を見かけないけど、ネットではしれっと活動再開。
例:徳井義実さん
活動休止後もNetflixのドラマに出演し、「テレビではNGでもネットではOK」という状態に。
これって、もう「テレビの世界に戻る必要すらない」というメッセージと思いませんか?
つまり、炎上や不祥事って、ある意味では「別の舞台へのキャリアチェンジ」のきっかけになっているんです。
なぜネットでは「被害者ポジション」が強いのか?
ネットの特徴として、「自分の物語を語れること」があります。テレビでは編集された一部しか映らなかったけど、ネットでは1時間でも2時間でも、自分の言葉で説明できる。
しかも、視聴者は「巨大メディア vs 一人の個人」みたいな構図に共感しやすい。だから、炎上した人が「個人として再出発」すると、意外と応援されるんですよね。
これは「共感」がベースにあるストーリー社会だからこそ可能な現象です。
これからのメディアと倫理観はどうなるのか?

では、今後どうなっていくのでしょうか?
テレビがブラック化する可能性
視聴率が下がり、スポンサーも「数字さえ取れればOK」となれば、テレビも多少グレーな人を使い始めるかもしれません。
ネットがホワイト化する可能性
逆に、YouTubeも広告主の意向で「クリーンなチャンネル優遇」が進み、暴露系や過激系は規制される可能性があります。
でも僕は、この2つが逆方向に歩み寄る未来よりも、むしろ
テレビとネットは、異なる価値観を持ったまま分裂し続ける
そんな未来の方がリアルだと思ってます。
つまり、「清潔さ」を求める人はテレビを見て、「人間臭さ」や「物語」を求める人はネットを見る。どちらかが消えることはなく、価値観に応じた棲み分けがどんどん進んでいくと考えています。
あなたはどちらの社会で生きたいですか?
「ルール社会 vs ストーリー社会」という対立は、今回のテーマにもそのまま当てはまります。
テレビはルール社会の最前線。ネットはストーリー社会の実験場。炎上を“終わり”ではなく“始まり”に変える力があるのが、ストーリー社会なんです。
僕自身、ネットでビジネスをやってきて、何度も思ったのは、「正しさ」よりも「共感の力」が時代を動かしているということです。
これからの時代、自分のストーリーを語れる人こそが生き残る、そう感じています。
さて、次回は「フェイクニュースが止まらない理由」と「今後のネット規制」について考えていきます。なぜ嘘の情報がここまで広がるのか? 本質に迫っていきます。お楽しみに!
「フェイクニュースが止まらない理由」と「今後のネット規制」についてはこちらの記事に書きました。

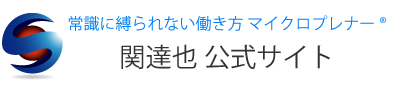
コメント